先日、あるラジオ番組に出演し、「リモートワーク時代におけるスタッフとのコミュニケーション」について語る機会をいただきました。
今回はその対話を振り返りながら、私自身が経験してきた変化と学びについてまとめてみたいと思います。
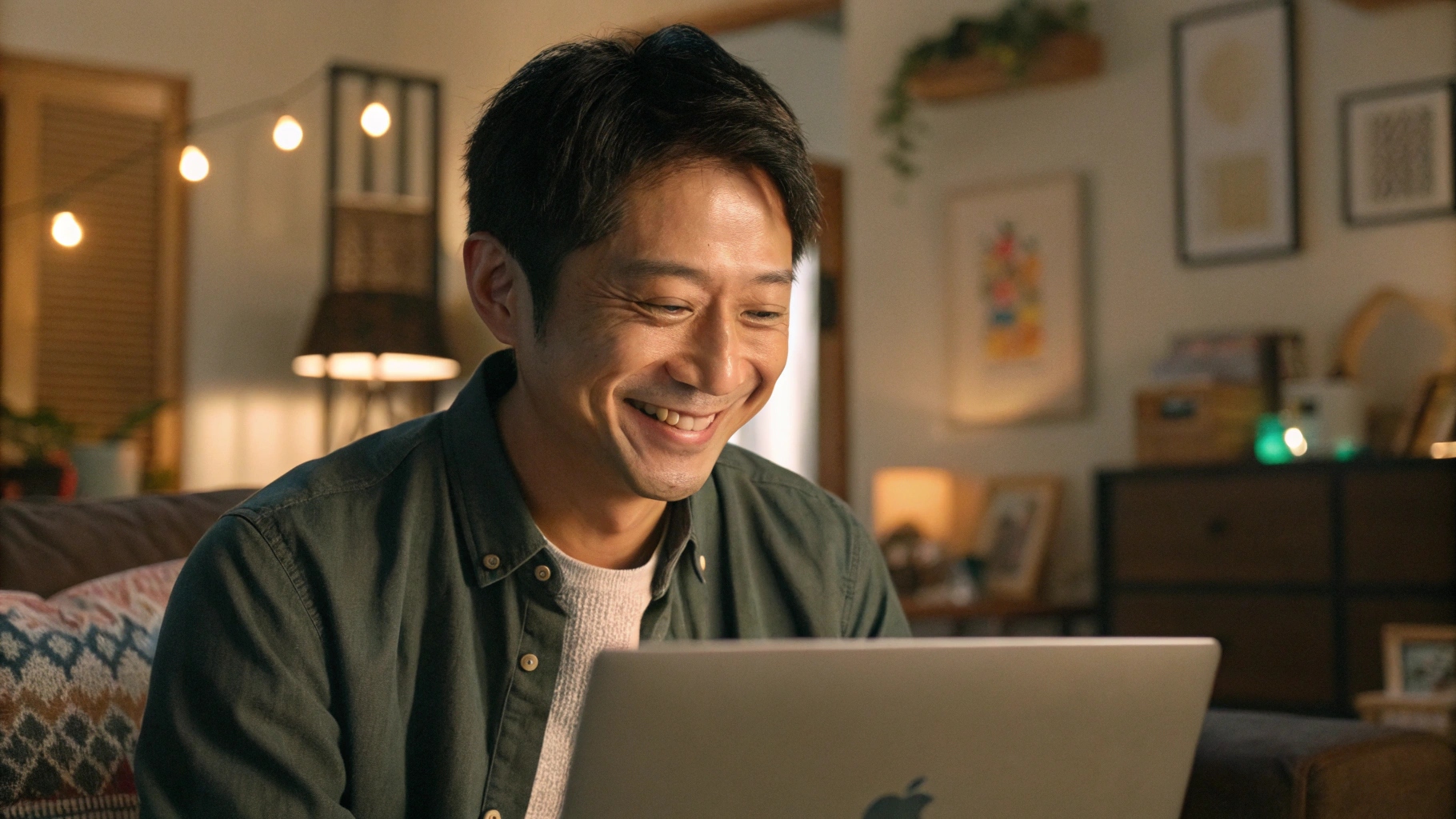
過去の私:一方通行のコミュニケーション
私はもともと、決して“聞き上手”なタイプではありませんでした。若い頃の私は「自分の考えを伝えたい」という欲求に突き動かされ、議論を好み、「説得=コミュニケーション」だと誤解していました。
その結果、しばしば空回りし、相手にとっては「話しづらい人」になっていたのだと思います。
気づきと転換:矢印を自分に向ける
ある時期から、自分のやり方が本当に機能しているのかを自問するようになりました。
日々の出来事をメモに残す習慣を通じて、後から冷静にやりとりを振り返ることができるようになり、「自分のコミュニケーションスタイルに課題がある」と気づきました。そこから、コミュニケーションは“キャッチボール”だという感覚を意識するようになりました。
キャッチボールとしての対話
相手が取りやすい球を投げる。相手の球を丁寧に受け取る。そして、リズムが整ったときに自分の直球を投げる。そんな感覚で会話を進めていくことが、今の私の基本姿勢です。
特に立場が異なる相手との間では、先に相手の主張を引き出すことで関係性が噛み合ってくるのを感じています。
リスペクトは“伝えて”初めて伝わる
私自身、心では相手を尊重していたつもりでも、言葉や態度でそれを伝えられていなかったことに気づきました。例えば、「あなたの意見を聞かせてください」という言い方を、「聞かせてくれる?」と柔らかく言い換えるだけで、随分と受け取られ方が変わるものです。リスペクトとは、思っているだけでは不十分で、“見える化”して伝える努力が必要なのです。
リモートワークだからこそ深まる対話
リモートでのやりとり、とくにチャットでは、言葉を「書いては消す」余裕が持てるため、感情の衝突を回避しやすいと感じています。
反射的に返してしまいそうな言葉も、一呼吸おいて冷静に見直せる。むしろリアルの場よりも、丁寧なキャッチボールができる場面すらあります。
本心を受け止める力
チャットでの対話でも、その人の発言の裏にある本心を読み取ろうとする姿勢が大切です。
日々のやりとりを通じて、相手の人となりを想像できる関係性があってこそ、言葉にならない“本音”にもアクセスできるようになります。そのためには、常日頃から「なぜこの言葉が出てきたのか」と、問いかける習慣を持つことが肝要です。
世代という幻想を超えて
番組の終盤では、ジェネレーションギャップについての話題も出ました。
私は「世代で人を分類する」という発想そのものに疑問を感じています。人は属性ではなく“固有の存在”であるべきです。一人ひとりと丁寧に向き合うことで、年齢や世代の違いは、ただの「違い」にすぎなくなります。
おわりに
こうして私は、コミュニケーションというものを、自己主張の場から“信頼のキャッチボール”へと再定義してきました。これはまだ道半ばの実践ですが、リモートという制約が、逆に私にとって“人を聴く”という本質を教えてくれたのだと思います。
今後も、スタッフ一人ひとりの個性と誠実に向き合いながら、組織における「関係性の質」を高めていけたらと願っています。
